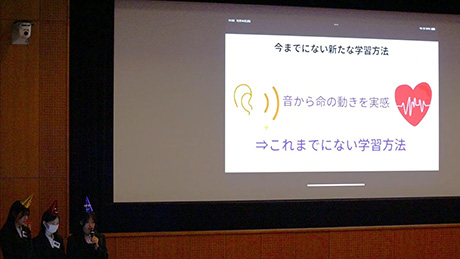生命理工学系 News
仕組みに乗る、仕組みをつくる
令和7年度第4回(通算第113回)蔵前ゼミ印象記
2025年7月18日、Zoom による遠隔講義にて、令和7年度第4回蔵前ゼミ(通算第113回)が開催されました。
蔵前ゼミは同窓生による学生・教職員のための講演会です。日本社会や経済をリードしている先輩が、これから社会に出る大学院生に熱いメッセージを送ります。卒業後の進路は?実社会が期待する技術者像は?
卒業後成功する技術者・研究者とは?など、就職活動(就活)とその後の人生の糧になります。
講師:谷口 一郎 先生
1984年 東京工業大学 工学部 機械工学科 卒業
1986年 東京工業大学 大学院総合理工学研究科 精密機械システム専攻 修士課程修了

講師の谷口 一郎 先生(タニコー株式会社)
当日の印象記を、広瀬茂久名誉教授が綴りました。その一部をご紹介します。
谷口さんは、日本最大の総合電機メーカー(日立製作所、従業員約26万人)でVTRの調整装置と可動式組立ロボットシステムの開発に関わった後、父親が創業した中堅の業務用厨房機器メーカー(タニコー、従業員1200人弱)でIH中華レンジ等の開発担当を経て、現在は同社の経営を率いている。両者を見比べることによって気づいた「よい点」と「悪い点」を後輩のために披露してくれた。谷口さんの学びを簡潔に表したのが標題の『仕組みに乗る、仕組みをつくる』だ。
1つの組織だけで働いていると、そこでの仕組みが“当たり前”となって、優れている点や弱点に気づきにくい。谷口さんも日立を離れて初めて、研究の支援体制の充実とチームワークによって、効率的かつスピーディーな開発が可能になっていること、そしてそれを支えているのは関係者全員での情報共有であることに気づいた。伝統ある組織の仕組みには、先達の知恵が込められており、なるべくその「仕組みに乗る」べきなのだ。しかし、仕組みに乗っかりっ放しでは、手順が確立していない“もの作り”には対処できず、新しいものは生まれない。このことはIH中華レンジという丸底鍋の電磁誘導加熱装置の開発で痛感した。状況に応じて「仕組みをつくる」ことも大事なのだ。
この他、「品質管理」、「経営」、「危機管理」に関する解説もなされた。これらに関しては詳細は省くが、次の点は強調しておきたい: いずれの項目においても、これまでに蓄積された先達の知恵に基づいて運用の“仕組み”(ISO9001、 電気用品安全法 etc.)が作られているので、それらの背景をも理解した上で、賢く利用して欲しいそうだ。谷口さんが危機管理を強く意識するようになったという“防げたかも知れない”「2000.3.8日比谷線中目黒駅列車脱線事故」については、やや詳しく説明したい。
印象記の続きは以下のPDFよりご覧ください。

「2025年度1Q2Q 蔵前ゼミを終えるにあたり」中島 肇(1977化工)蔵前工業会神奈川県支部長
皆さんご存知のとおり、蔵前工業会は東京科学大学の理工学系同窓会です。本日の講師の谷口さんとは一緒に蔵前工業会の理事として本部の運営に携わっています。今日お話を伺って、谷口さんのバックグラウンドをより深く理解できました。谷口さんの会社は、BtoB事業で私たちが世話になっている外食産業を支え、ひいては社会を支えています。さらに言えば最近のインバウンド需要で注目されている外国からのお客様への「日本の食」の提供も支えていると思います。非常に面白いお話を聞かせて頂きました。
本日は蔵前ゼミの今期の最終会でしたが、4回通して参加いただいた学生の皆さん 有難うございました。質問の部も盛り上がっていたように思います。卒業後の進路やこれからの実社会で求められる「プロフェッショナル」について どうあるべきか、深く学ぶ機会を提供できたのではないかと大変うれしく思っています。
今回で113回目となる蔵前ゼミですが、先輩からの貴重な経験談やアドバイスを通じて、将来、皆さんのキャリアにおいて成功するためのポイントについて熱いメッセージが一貫して届けられてきました。今期の計4回のゼミでも技術者や研究者として、また一社会人として必要なマインドセットについて皆さんにとっても深く考える貴重な機会になったのではないでしょうか。今後とも私たち蔵前工業会は、皆さんにキャリア及び就職支援サービスを続けていきます。その辺を通じて皆さんが将来Science Tokyoが掲げる「科学の進歩と人々の幸福」というスローガン実現の担い手になってくれることを心から期待しています。
少し具体的な話なりますが、蔵前工業会の就職支援サービスとして次の大きなイベントが準備されています:2025年11月5~7日の3日間、「蔵前企業研究会」(K-find)![]() が蔵前会館で対面方式で行われます。約200社が参加し、各社がブースを出して、皆さんを歓迎してくれます。毎回好評を得ている一大イベントです。今後ダイレクトメールや研究室宛に参加募集のポスターやビラが配布されると思いますので、是非ご参加ください。
が蔵前会館で対面方式で行われます。約200社が参加し、各社がブースを出して、皆さんを歓迎してくれます。毎回好評を得ている一大イベントです。今後ダイレクトメールや研究室宛に参加募集のポスターやビラが配布されると思いますので、是非ご参加ください。
最後になりましたが、蔵前ゼミの開催に際し、講師を務めて頂いた同窓の方々及び多大なご支援ご協力を賜りました「企業社会論」担当の中戸川先生を始めとする大学関係の皆様に感謝申し上げます。

勝丸泰志(やすゆき、1977電気)蔵前ゼミ担当チーフ幹事からのコメント
この度は蔵前ゼミにご登壇いただき、誠にありがとうございました。事前に頂きましたポスター用の写真に日の丸を見た時に、なぜ、と思いましたが、東日本大震災の復興に関係していたとは思いもよりませんでした。そのような大切な写真をカットしましょうかと言わなくてよかったとほっとしています。
ご講演では、会社の仕事や経営を仕組みの観点で説明していただきました。「仕組みに乗る、仕組みをつくる」とのテーマを拝見した時、良いテーマだなと思いました。
大会社と中小会社を対比して、仕組みの有無についてお話しいただきました。多くの学生は大企業への就職を考えていると思いますが、仕組みが整っていてサポートが豊富な(大企業の)環境で仕事をすることと、自分でやらなければいけないことが多く仕組みが十分でない中小企業で仕事をすること、という見方は学生に企業に対する新たな視点を与えたのではないかと思います。
品質管理では、共通語で話ができ同じ品質で生産できる体制を維持するための属人的ではない管理、経営管理では、法令・基準にあわせた管理、危機管理では、危機を未然に防ぐために事故事例に学ぶことを仕組みとすることなどをお話しいただきました。研究中心の活動をしている学生には、何かを仕組みで保証するということを学ぶ機会は少ないかもしれませんので、これらのお話を聞いて企業で仕事をするということを多少なりとも想像できたかもしれません。
組織で仕事をした経験のある人にはよくわかる話ですが、学生がどこまで理解できるかなと少し心配していました。しかし、質問を聞いた限りでは杞憂のようでした。仕組みで動くことと自立的に動くこととの使い分け、仕組みと直観とのそれぞれの意義などの良い質問があったので、理解してもらえたと思いますし、ISO 9001導入の時の社員の反応など、現実を想像することもできているようで安心しました。
2025年度企業社会論における最後の蔵前ゼミに相応しい有意義なご講演に感謝申し上げます。谷口様のこれからの益々のご活躍とご健勝、そしてタニコー株式会社様のご発展を祈念いたしますと共に、今後とも蔵前工業会神奈川県支部へのご支援を賜りますようお願い申し上げます。