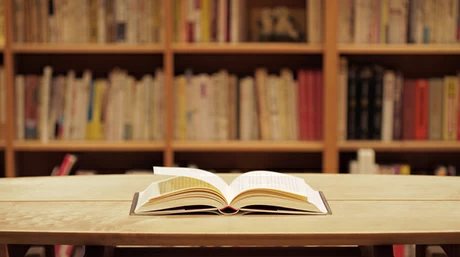リベラルアーツ研究教育院 News
異なる視点が交わる「共修」の場で学ぶ、多様性と未来を創る力
~リベラルアーツ研究教育院 統合記念シンポジウムを開催~

開会の挨拶をするリベラルアーツ研究教育院長の室田真男教授
2025年8月4日、「リベラルアーツ研究教育院 統合記念シンポジウム『世界を広げ 未来を輝かそう』」(主催:東京科学大学(Science Tokyo)リベラルアーツ研究教育院(ILA))が開催されました。ハイブリッド方式で開催され、会場とオンライン、合わせて約150名が参加しました。
ILAは、旧東京医科歯科大学教養部と旧東京工業大学リベラルアーツ研究教育院が統合して、2024年10月に設立した組織で、Science Tokyoのリベラルアーツ教育を担当しています。統合後、医歯学系・理工学系の異なる専門の学生が学び合う「共修」の実践をいち早く進める中でILAでは、2025年度の第1クオーターには、両学系の新入生が大岡山キャンパスでともに学ぶ「大岡山Day」を実施しました。「大岡山Day」では、互いの専門分野や価値観に触れ、視野を広げることを目指し、少人数クラスでの対話型学習を軸にした必修科目「立志プロジェクト」とオムニバス科目「人文社会科学概論」が開講されました。本シンポジウムは、統合後のリベラルアーツ教育での「共修」の取り組みとその成果を紹介し、今後の課題と可能性を議論・展望する機会として開催されました。

冒頭で挨拶と期待の言葉を述べる田中雄二郎学長(左)、 閉会の挨拶と今後の共修への期待を語る大竹尚登理事長(右)
「大岡山Day」について
第1クオーターの月曜日は「大岡山Day」として、医歯学系と理工学系、すべての新入生が大岡山キャンパスに集まり、「立志プロジェクト」を受講します。また、同日の9-10時限には、医歯学系の必修科目「人文社会科学概論」が理工学系の学生にも向けて開講されました。
多様な対話が生む、理解の広がりと深まり

シンポジウムではまず、統合前の旧東京医科歯科大学の教養教育、旧東京工業大学のリベラルアーツ教育の概要説明があった後、「大岡山Day」について紹介されました。そして、この取り組みによって学生・教員双方に大きな変化が見られたことが報告されました。

「大岡山Day」の内容について説明する、リベラルアーツ研究教育院の薩摩竜郎准教授(左:ILA大岡山)と藤井達夫教授(右:ILA国府台)
その後、実際に授業を受けた新入生と授業を支援した大学院生が登壇して、パネルディスカッションが行われました。そこでは、「立志プロジェクト」の中で、医歯学系と理工学系それぞれに属する学生が同じクラス内のグループで一緒になった結果、これまで接点のなかった分野(例:公害、遠隔医療、オルガノイド※など)に関して、互いの視点から探究する機会が生まれ、新しい発想が育まれたというエピソードが紹介されました。
また、所属する学部・学院を超えた交流が深まり連帯感の醸成などが見られたという意見が紹介されました。多様な視点が議論を活発化させ、互いの学びを深める相乗効果を生み出したことが示されました。
※:人工的に作られた立体的な細胞の集合体。幹細胞(iPS細胞など)から培養され、実際の臓器に似た構造や機能を持っている

学生パネルのモデレータをつとめた鈴木健雄講師(左:ILA大岡山)、学生らと談笑する田中雄二郎 東京科学大学学長(右)
登壇した学生からは、その他に「知らない人同士での意見交換は緊張して大変だったが、最終的には仲良くなった」「自分にない意見を知ることができて刺激になった」「新しい視点を見つけることができてうれしかった」「最終プレゼンテーションは自分が計画立ててグループをまとめることになったが、結果的に非常に良い経験になった」「せっかく医歯学系と理工学系の学生が一緒になる授業なのに、5月末で終了というのは短い」といった意見が聞かれました。
課題を糧に次なる成長のステップへ

続いて教員によるパネルディスカッション※が行われ、2025年度実施の「大岡山Day」を振り返りました。登壇者からは、「新たな授業を始めるにあたり、これまでとは違う苦労や工夫があり当初は不安を感じた」という声もあった一方で、「最終的には学生からの満足度も高く、多くの学生の成長を実感することができたと」して安堵の声が聞かれました。
※パネルディスカッション参加者(順不同)
檜枝光憲教授(ILA国府台)、永岑光恵教授(ILA大岡山)、猪熊恵子准教授(ILA国府台)、赤羽早苗准教授(ILA大岡山:英語クラス担当)、岡田佐織准教授(ILA大岡山:モデレーター)

パネルディスカッショではその他、「今回の『立志プロジェクト』では、DE&I※1、コンバージェンスサイエンス※2、水俣病と科学者倫理といった横断的なテーマが中心に据えられ、これにより、学生は社会の複雑な課題について多角的に考える力を養うことができたのではないか」といった意見や、「旧東京医科歯科大学の『グローバル教養総合講座』の“深さ”は一部減衰した感はあるが、学系横断の“広がり”が大きく増幅。短期間でも高品質なアウトプットが多数あった」という声、「最終発表をグループで行う形式に変更したことで、知識をインプットするだけでなく、チームで協働してアウトプットする力が身についた」といった声などがあり、「共修」の場としての成果が振り返られました。
※1:Diversity(多様性)、Equity(公平性)、Inclusion(包摂性)、多様性を認め、誰もが公平に、自分らしくいられる環境づくりを目指す考え方
※2:コンバージェンス サイエンス(Convergence Science)とは、異なる分野の知識、手法、視点を統合し、複雑な社会課題や科学的な難題の解決を目指す学際的なアプローチのことで、個々の学問分野が緊密に連携し、新たな科学的知見や技術革新を生み出すことを目的とする取り組みを指します

一方で、英語で開講されている留学生クラスでの今後の共修の可能性について、「日本人学生との混成クラスの編成や、留学生と日本人学生とで対話する機会を制度化するなど、多様性を考慮した科目編成とその最適化の検討が必要である」といった課題提起がなされました。また、本取り組みの評価については、長期的な教育効果の測定実施が重要であるとし、大学が実施している卒業生を対象としたアンケート結果など、中長期での教養教育の効果(5~10年スパン)を把握する仕組みを活用し、強化する必要があるとの意見も出されました。

合わせて、初年度ならではの課題として、システム統合による運用に混乱があったことが紹介されました。次年度に向けては、それらの改善とともに、学生から寄せられた「授業の回数や共修の機会を増やしてほしい」といった要望に対してどう向き合えるか、さらに学びを深められる環境を整備していくことへの必要性についても言及されました。
統合後生まれた、新生リベラルアーツ研究教育院が目指す「共修」は、異なる学系に属する学生と教職員が、従来の枠を超えて協働し、共に成長する場として、Science Tokyoの新しい教育モデルの核となるものです。今後も、学生と教職員が一体となって取り組みを深化させることで、より質の高い学びの場が創出されることが期待されます。
※ 2025年12月4日 本文の一部を修正しました。