リベラルアーツ研究教育院 News
自分の知識や技術を何のために使うのか それを考えさせるのが教養過程における私のミッション
【技術史】河西 棟馬 講師
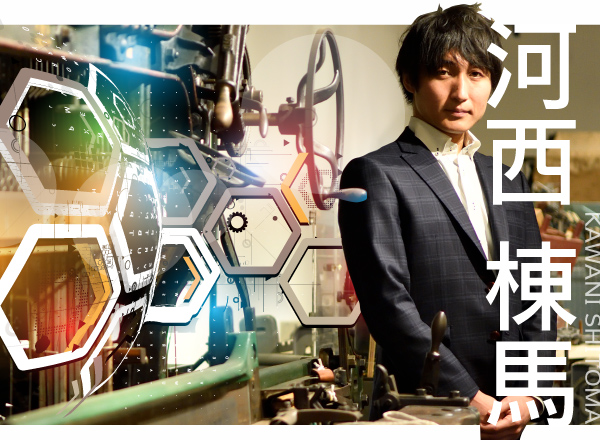
日本の技術史とは
切っても切れない東工大の足跡
私は技術史の担当講師として、通年で「技術史」の講義を担当します。ただし一口に技術史といっても、その切り口は極めて多様です。歴史学は単に昔のことを調べる学問ではなく、今ある世界がなぜこのようになっているのか、こうなるまでにはどのような歴史的展開があったかを研究する学問です。問いかけなくして歴史学はありえません。そしてその問を立てるのは現在という時間軸を生きている歴史家です。問が変われば当然ながら切り口も変わってきます。歴史とは常に「現在」というレンズを通して見た過去の像であって、我々が置かれている歴史的位相が常に変化の過程にある以上、歴史は常に改訂の過程にあります。
技術史も歴史学の一分野である以上、これと同じことが言えます。さしあたり、東工大では私が関心を持っている4つのアプローチから「技術史」について論じていこうと思っています。先程「問なくして歴史学はありえない」と言いましたけれど、その問が私個人に閉じた問であってはやはり意味がありません。現代の世界、現代の日本を考える上で、誰もが考えておくべき問というものがあります。大学という場で教える以上、そうした公共性の高い問を立てて論じるべきだろうと思います。また、エンジニア候補生である東工大の学生だからこそ考えて置かねばならない問というのもあるはずです。そのため、「なるべくスタンダードな歴史記述であること」「技術/技術者についての反省的理解を促すものであること」を意識して題材やテキストを選ぶように心がけています。
詳しくはシラバスを参照して貰えばよいかと思いますが、「技術史A」 では技術者という職業集団の歴史、「技術史B 」ではオーソドックスな西洋技術史、「技術史C」 では技術という概念の歴史、「文系エッセンス(技術史)」については、技術史研究の現在について紹介していこうと考えています。一般に「技術」というとき、それはしばしば両者が渾然一体となった「科学技術」のことを意味しています。しかし、もとはといえば科学と技術は別物です。両者が互いに接近・混交して「科学技術」「技術的科学」となっていったところに、西洋科学史・技術史の一つの特徴があります。「科学技術」は長い歴史を経て19世紀の西洋で確立し、それ以外の地域はみなその模倣・学習を強いられました。そのため、「科学技術」の来歴を考えようとするとどうしても西洋中心の記述にならざるをえず、技術史A-Cでも西洋中心の記述が多くなります。しかし昨今ではグローバル・ヒストリーなどの視点を取り入れた新しいタイプの技術史を描き出そうとする試みが活性化しています。大学院生向けの講義ではそうした新しい潮流を中心に紹介していきたいと思っています。
東工大は私の研究と関係の深い大学でもあります。日本の工業教育史上において東工大は極めて重要な存在であり、東京職工学校から東京高等工業学校を経て1929 年の大学昇格に至る流れは一通り勉強したことがあります。また、初代の電気工学科の教授を務めた鯨井恒太郎は私の博士論文の重要人物の一人で、彼の教え子でやはり教授になった古賀逸策、戦前の工業教員養成所のほうの卒業生である高柳健次郎、そして1942 年から学長を務めた八木秀次など、東工大は日本技術史上の重要人物が多数在籍した場所です。
日本の技術史を調べていると、ほとんど至るところで東工大関係者にでくわします。日本のエンジニアリングの歴史はこの学校を抜きにしては語れず、技術史研究者としてもここで研究と教育に当たれることはありがたく思っています。
IT産業を下支えするインフラこそ
現代の技術基盤
私は修士課程まではコンピューティング史という分野の研究をしており、現在もその延長上で電気通信技術の歴史を専門に研究しています。しかし、コンピュータやインターネット、人工知能が重要な技術であることは、現代人にとっては自明です。しかもそれが「革命的」であることはあまりに喧伝され過ぎているように思います。確かに情報処理速度の加速度的増加によって、生活のさまざまな場面が電子化されているのは皆さんご存知のとおりです。ですが、そもそも電力インフラと通信インフラがなければインターネットもコンピュータも機能しません。
現在、情報通信技術が重視されている最大の理由はその経済的存在感にあります。企業の時価総額ランキングを見るとアメリカのGAFAM[グーグル、アップル、フェイスブック(現メタ)、アマゾン、マイクロソフト] や中国系のアリババやテンセントといった巨大企業が軒並み上位を占めています。
しかし、重要性の尺度は経済だけではありません。我々は市場価値によってものごとの重要性を図ることにあまりにも慣れすぎていると思います。地味かもしれませんが、上下水道技術や道路建設といった土木技術、農機具から殺虫剤に至るまでの農業技術、そしてガラスからプラスチックや合成染料といった化学技術は今なお現代社会の基盤をなしています。そしてこれらの重要性は、情報通信技術のような「最先端」に比して十分に認識されているとは思えないのです。
ここで勘違いしないでほしいのですが、私は経済的なものの見方は極めて大事だと考えています。実際、技術史は経済学(特に経済史)との密接な関わりのもとに発展してきた分野です。そして、経済を無視した技術史は、それはそれで不健全です。私が言いたいのは「それだけではない」ということです。
こうした判断から、講義では私の専門の込み入った議論はなるべく封印して、技術というモノやないしアイデアの歴史について、なるべく鳥瞰的な視点から論じていきたいと思っています。よく言われることですが、「専門」の敵は「教養」です。歴史的にも両者は敵対してきました。しかし、これらは現代の市民にとっては車の両輪だとも思うのです。専門家なくして現代の社会は絶対に運用できません。しかし他方で、あまり詳細に立ち入りすぎれば、却って大きな、公共的な問は立てられなくなります。
この世の中には、専門的知識で解決できる問題もあれば、幅広い知識を総動員して初めてアプローチできる問題というものもあります。私が担当するのは教養科目ですので、後者のタイプの問いかけに役立つような知識と方法とを講じるのが仕事だと認識しています。それにどうせ、みんな嫌でも自分の専門では細々としたことをするのです。マックス・ウェーバーが100 年前に言っていたことは今も正しく(『職業としての学問』岩波文庫、1980邦訳21〜22ページ)、専門的詳細に命をかけることができない人間は学者にも専門家にもなれません。我々はみな何らかの対象については専門家であり、それ以外の問題に対しては素人とならざるを得ない世の中を生きています。教養教育の仕事は、こうした世の中にあってバランスの取れた良識ある判断を下すことのできる人材を養成することにあると考えています。
理系コンプレックスから始まった研究
結局はデジタルからアナログへ行き着く

高校の頃から漠然と学者になりたい思いはありました。私は千葉県立千葉高校の出身ですが、今思えば私がいた頃のあの高校には、大学よりも大学らしい雰囲気がありました。実際あの頃の地方名門高校の教員というのは、新左翼もニューアカも一通り経験した、最後の教養主義者たちの世代だったのではと邪推しています。
京大文学部に入ったのは単に文系科目のほうが得意で好きだったからで、特に深い理由はありませんでした。大学に入ってからは本を乱読しました。学部三回生のときに「科学哲学科学史」という専修に進んだのですが、一つのきっかけは夏目漱石でした。専修を選ばなくてはいけなくなった頃、私はたまたま漱石の書いたものをよく読んでいました。そんな折に、漱石が「英文学なんて専門を選んだのは失敗だった、学問をするなら普遍的なものに限る」というようなことを言っているのを読みました。
漱石は文学者だから自然科学のことなんて知らない人なのだろうと思っていたのですが、これは大間違いで、彼は一時期かなり集中的に理科系の学問を学んでいることをその時に知りました。物理学者の寺田寅彦が門下にいて(『三四郎』に寺田をモデルにしたとされるキャラクターが出てくるのは有名)、寺田が漱石の理解の高さを褒めている文章もどこかで読みました。
その頃から、私の中で理系コンプレックスが頭をもたげてきました。当時の私は、世界を半分学びそこねているような気分になっていたのです。そんなことを考えるようになったもう一つのきっかけが池澤夏樹さんの著作でした。『スティル・ライフ』は何回も読んだ今も大好きな小説です。池澤さんも理科系出身ですが、彼の初期の小説に特徴的な、人間をどこか突き放したような文体は、自然科学的なものの見方を知っているからこそのものでしょう。こんな風に世界なり自然なりを見れるようになりたい、と思ったことを覚えています。
その頃の私は「歴史的なアプローチであれば、科学なり技術なりについて、今からでもある程度は学べるのではないか」と思っていました。そんな思いもあって京大の科哲史研究室に進み、そうこうするうちに卒論のテーマを決めねばならなくなりました。私が技術史へ流れつくことになったのは、このときにコンピュータの歴史を卒論のテーマにしたことによります。私の師匠の伊藤和行先生はガリレオ研究者であり、イタリア・ルネサンス研究者であり、物理学史家でありましたが、一種のサイドプロジェクトとしてコンピュータの歴史にも関心を寄せておられました。当時はあまり認めたくなかったので認識できていませんでしたが、今思えばコンピュータを対象に選んだのも、やはりこれが私の知的コンプレックスの由来の一つだったからだと思います。
毎日使っているのに、中で何がどう動いているのかさっぱりわからない。かたやIT 強者は偉そうに情弱をバカにする。それで、「じゃあコンピュータ科学をいっちょ歴史とセットで勉強してやろうじゃないか」と思った。しかし、いざ勉強してみたら、ずっと避けてきた理科系の学問というものが案外面白いものでした。その後も紆余曲折があったわけですが、気づけば私は物理や数学が(レベルは低いにせよ)好きになっていました。
そうこうしているうちに私の関心は物理学と工学の関係はどうなっているのか、というところに向かっていきました。コンピュータ科学は基本的には離散的対象を扱う、代数学的な手法を基礎としているように思うのですが、現実世界というのは基本的には解析学的な手法によって記述される、アナログで連続的な世界です(量子力学のようなミクロな世界のことはいったん考えないこととします)。実際、電気電子回路の教科書なんかを読むと基本的にはアナログな式しか出てこないのに対し、スイッチング回路の話になると離散数学の話しか出てこない。
それで、「アナログな電気工学からデジタルなコンピュータ科学へのジャンプというのは歴史的にどう起きたのだろう」「計算機科学というが、これは科学というより工学なのでは?」「そもそも工学と科学というのはどのような関係にあるのか」というところが気になって研究を進めていきました。そんな成果をまとめた論文が私の最初の英語論文でした。
その研究の過程で、私の関心は現代的でデジタルな計算機科学やインターネットの世界から、アナログな電気電子工学、特に通信工学の方へとシフトしていきました。今も私はこの研究の延長上で仕事をしています。
グローバル・ヒストリー的な技術史のアプローチからは
今までにない面白さが見えてくる

技術史や科学史といった分野の歴史をたどっていくと、どちらもその力点を「技術」や「科学」そのものから、「歴史」の方向へと移行させていったことがわかります。かつての技術史家たちは「技術」が大事だからその歴史をやっていた、現代の技術史家たちは「歴史」が大事だという判断から技術史を研究しているように見受けられます。
今の技術史はもはや完全に人文学の一部です。2021 年にパンデミック真っ最中にもかかわらず奨学金をもらって1 年弱アメリカに行ってきたのですが、現実の状況は思っていたよりもさらに先鋭的でした。ジェンダー・人種・階級、帝国主義とポストコロニアリズム、あるいは人新生の議論と結びついた環境史の議論が大流行しているのに対し、技術そのものの発展に関心を持って研究をしている歴史家はほとんど見かけませんでした。私は現在の状況は少々行き過ぎだと思いますが、しかしそれでもこうした研究潮流から学べることは多いと考えています。
今の私が特に惹かれているのはグローバル・ヒストリー的な技術史のアプローチです。例えば私の扱ってきた科学者・技術者たちは、米国のMIT(マサチューセッツ工科大学) を卒業してベル研究所に入った、あるいは日本の帝国大学を卒業して日本電気に入った技術者などです。しかし彼らは科学者・技術者である以前にエリート教育を受けた人物であり、「企業研究所」という組織に勤めるサラリーマンでもあるわけです。そして科学者や技術者が企業のサラリーマンになるという事態そのものが、科学と技術が企業資本主義や国家を媒介として融合する、というグローバルな歴史的変化の現れでもありました。
「企業研究所」という存在は19 世紀にドイツで生まれアメリカで成長し、20世紀において大学と並ぶ重要な研究拠点に育っていきます。そして彼らが生み出す知識やモノというのは、特許などの制度を介して、19 世紀末から20 世紀初頭の「帝国の時代」においてグローバル大企業の国際カルテルを下支えすることになります。技術水準の高さはまた、しばしば「高い文明」の象徴とされ、帝国主義支配を正当化する武器として見られていたことも研究の過程でよく見えてくるようになりました。
特に日本の場合、「西洋技術によって日本人が植民地支配を正当化する」ことの矛盾が、当時のエンジニアを鬱屈に追い込み、また熱烈な国産化に向かって駆り立てた、という事情もわかってきました。技術は人間に可能な行為の幅を規定するものであり、それは緩やかに歴史の流れを規定します。そしてその時々の特異でローカルな事情もまた、技術の形を緩やかに規定します。技術史とグローバル・ヒストリーのインタラクションはそれ自体としても興味深いものですが、それを理解しておくことは、現在の我々が置かれている時代状況を理解する上でも有用であろうと思います。
私が考える教養、リベラルアーツとは
私は教養という言葉に対して、愛憎渦巻く複雑な感情を抱いています。教養論は日本の文芸ジャンルとして定着している感があり、Amazon で「教養」をキーワードに検索すると数限りない「教養本」が出てきます。しかも教養論は大正教養主義の時代から数えれば100 年近い歴史を誇ります。
現在出ている教養本の多くは雑学本ないしは分野入門のような本ですが、「教養」を正面から論じた本を読む限り、この言葉に独特の「いやらしさ」があることはほぼ誰しもが納得するかと思います。
他方で、「教養」なるものを備えた知識人には、一昔前まで人を平伏させずにはおかないような圧倒的なオーラがありました。圧倒的な知性と学識によって天下を睥睨(へいげい)する偉い学者、というのは確かにいたのです。
私の場合だったら、イギリスの歴史家エリック・ホブズボームや、日本であれば加藤周一、あるいはちょっと路線が違いますが朝永振一郎などがそういう知識人にあたります。朝永は散文でも良いものを書きました。そして、そういう存在に対する畏敬の念がなければ、誰も学者なんか目指さないと思うのです。ホブズボームが当代一流の歴史学者であったと同時にジャズ批評家でもあったという事実を前にして、打ちひしがれながらも痺れてしまう感性というのが、私にとっての教養主義です。
今回、教養教育の機関に就職することが決まったので、山のようにある教養論から何冊かをピックアップして読んでみたのですが、一般論的(人生論的とも言えるかもしれない)教養論の中では、戸田山和久先生の本が一番自分の考えと近いものでした。なので、私ごときが何か言うよりは戸田山先生の『教養の書』(筑摩書房、2020)を読むことを学生さんに勧めてお茶を濁したいところです。
日本の教養主義の歴史的分析については竹内洋『教養主義の没落』(中公新書、2003)と高田里恵子『グロテスクな教養』(ちくま新書、2005)のセットが大変勉強になりました。竹内の本は、学部生の頃に読んで衝撃を受けた本の一つです。再読して改めてグッと来ました。本書はピエール・ブルデューの社会学理論をフル活用しながら、「教養」が人をランク付けし値踏みする道具として機能してきたことを鮮やかに説明し、そしてそれが戦後の日本で徐々に機能しなくなっていく過程も見事に描き出しています。これは社会科学的分析のお手本としても読める素晴らしい仕事です。
そのアンチテーゼとでも言うべき本が高田の本です。最近初めて読んだのですが、ときに痛々しい気分になりながら、ときにゲラゲラ笑いながら読みました。『教養主義の没落』がすでに没落した「教養主義」を学者的に突き放しつつ、しかしノスタルジアを込めて描いているのに対し、『グロテスクな教養』は教養主義の「いやったらしさ」を女性研究者の視点からこれでもかというほどに描き出しています。どちらも名著です。
おわりに
最後に伝えたいのは、技術というものは何かしらの目的に対する手段である、ということです。技術の内部からそれが奉仕すべき目的を導き出すことはできません。ですから、学生の皆さんは「何のために自分の技術や専門知識を使うのか」を考えておかなくてはなりません。
技術史は古代以来軍事史と切っても切れない関係にあります。英語のエンジン engine はもともと「兵器」のことを意味し、エンジニアengineer はもともと「工兵」すなわち軍事技術者を表す言葉でした(今も軍事的な文脈ではその意味で使われています)。技術と軍・国家との結びつきは今後も続くでしょう。技術史は学んでいて楽しい分野ではありますが、同時に重く苦い歴史にも満ちています。そうした過去を踏まえた上で、「どんな大義のために自分の能力を使うのか」「何が現代にあって重要な技術か」「技術にとって重要性とは何か」ということを技術者予備軍の学生は一度考えておいたほうがいいと思います。そして、それを考えてもらう手助けをするのが教養過程における私のミッションです。
![]()
河西 棟馬 講師
研究分野 技術史

1990年生まれ。京都大学文学部卒。2020年3月研究科科学哲学科学史博士後期課程単位取得退学。2021年3月ヴァージニア工科大学客員研究員(大学院博士論文研究プログラム、フルブライト奨学生)。2022年4月より現職。日本科学史学会会員。







