リベラルアーツ研究教育院 News
アカデミックな状況で通用する英語の基盤を育成する
【イギリス小説】原田 大介 准教授

毎回の課題を提出するだけでも
力はついていく
語学の英語についてですが、学士課程の1、2年生を中心に教えています。
授業は、時間内で済ませる課題と持ち帰りの宿題という2種類の提出でまとめられるように構成しています。東工大生に英語を教えるにあたって重視しているのは、最初にこの2つの課題と宿題をきっちりやらなきゃいけないんだ、と知らせることです。2つを真面目にやっていれば、こちらが狙う結果が出てくる設計です。ちょっと不具合があっても、とにかく必ず提出するようにと念を押しています。多少遅れてもすべての課題と宿題にしっかり取り組んで提出してくる学生は、期末には確実に語学力をアップさせています。
学生たちに伝えているのは、英語に関する問題の答えは選択肢A、B、Cなどという記号では決してない、ということです。言葉ですから当然です。文章を書くときには、伝える内容と目的、それに相手—読み手—を考えて、ひとつひとつの文に役割を与えながらパラグラフと文章全体を構成するよう強調しています。日本語の文章をつくるのと同じです。
いささか昔話になりますが、私たちの学生時代は、テレビでは外国映画を毎日のように放映していましたが、ほとんどすべて日本語吹き替えでした。ごくまれに字幕放送があると、カセットテープレコーダーを持ってテレビの前に座り込んだものです。そうやって録音したものやFEN(駐留米軍向けラジオ放送—現在はAFNと改称されています)の定時ニュースをまるごと全部書き起こすことをしました。英語に直接触れるにはそれくらいしかありませんでした。現在は逆にあまりに英語を手軽に学ぶ環境がインターネット上にあるため、かえって何をどう学べばいいか迷っている、手をつけそこねている、という人が少なくないと思います。
たしかに最近の学生は、チャンスが増えたせいでしょう、英語の「音」については耳でしっかり聞けるようになっています。ところが、少しまとまった量になると、話の流れをとらえきれず、問いかけをしても短い一言で答えきったつもりでいたり、オウム返しですまそうとする傾向が目立ちます。マークシート式の問いと答えのようだといえるでしょう。けれども、英語は言葉ですから、そういう一問一答式な姿勢では実際に会話をしたり、文章を書いて相手とかかわりあっていくことはできません。
だから、私の授業では、ひとつひとつの文をしっかり書かせて、さらにそれぞれの文が一つのパラグラフになるよう論理的に構成させる訓練を行っています。自分の考えを英語でまとめて文章にする、というのを繰り返す。基礎を身に付けることではじめて、自分の専門のアカデミックな分野で英語を活用できるようになる。その意味でも、学士課程の最初2年間の英語教育はとても重要です。実際そのために英語科目を担当する教員の間では、カリキュラムを工夫し、ブラッシュアップするための活動が継続して行われています。
学士課程の1年目2年目の授業には、クラスごとに何人かは、こちらから何も言わずとも十分こなせる程に英語に習熟した学生がいます。むしろ気にかかるのは、頑張っても成果が出ない学生です。たとえば再履修のクラスや、あるいはTOEFLの一定のスコアを求める3年目以降の英語科目で、なかなか目標に届かない学生に対して、どうすればいいのかを日々考えています。
東工大の学生のほとんどは将来、研究者か技術者となります。どちらの職についても英語は必須です。世界最先端の分野に接する仕事ですから、必然的に英語で情報を収集し、英語でコミュニケーションをとる状況の中にいやおうなく放りこまれます。
その点、大学院生ともなると、英語は仕事に必須、という自覚が固まってきます。英語の授業にも積極的に取り組み、相当しっかり使えるようになってきます。しゃべらせると少々たどたどしい場合でも、とにかく伝えてやるんだ、聞いてやるんだという気構えが出てきます。
当時の伝統や時代そのものが詰まった
長編小説に魅せられて

私の専門は、18世紀の長編小説『トム・ジョウンズ』の研究から始まりました。イギリス小説の父ともよばれるヘンリー・フィールディングの作品で、一種のオリジンに近いところから研究してみたいと思い、手に取りました。ただ、結局は長い小説が好きだというところに行き着くのだと思います。
19世紀ヴィクトリア朝のディケンズやサッカレーにしても、月刊分冊の形で1年半以上もかけて発表されるものが多いんですよね。十数カ月もの間、読者を引きつけて、出来上がった作品はペーパーバックで800~900ページにもなる。分量が多いだけに何でもかんでも入ってくるわけです。
主人公の人間関係や、全体を貫く物語はもちろん、その時代の政治や経済、法律、教育、生活全般がそのまま生きて入っています。一方でギリシア、ラテンの古典教養につながる要素もある。当時の伝統や時代といったあらゆるものが詰まっている。読む側の時代の意識も反映される。まさに総合的な教養がてんこもり。ゆえに時間をかけて研究するかいもあります。
中学生、高校生だったころ、英語の原著で小説を読み始めました。きっかけは、単純に英語の成績が少しでもよくなるかなという理由でした。最初に手に取ったのは『メアリー・ポピンズ』でした。映画は有名だし、主題歌はポピュラーだし、児童文学だからわかりやすいだろうと思ったんですね。
今から思えば、とんでもないものを最初に選んだと思います。児童文学はそれこそ伝統の塊です。たとえば、英文学者の新井潤美東大教授が『不機嫌なメアリー・ポピンズ イギリス小説と映画から読む「階級」』の中で解きほぐしているように、メアリー・ポピンズの職業であるナニーには英国の階級にまつわる複雑な意識が込められていますし、同時に物語の中の細かいエピソードにはさまざまな学芸、古典につながる発想が含まれています。
それを知っている今だと、かえっておいそれと手の出せない「難関」に見えます。同じことは『ドリトル先生』シリーズにも『ハリー・ポッター』シリーズにもいえます。出てくる呪文がラテン語の流れを色濃く反映したものだったりします。
児童文学には、それぞれの国の文化と歴史が練りこまれています。それを息を吸うように自然に子供たちが読んでいく。つまり、その国の文化と歴史を体得するわけです。彼らが大人になり、文化と歴史を引き継ぎながら、次の社会をつくっていく。文学にはそういう力がある。そんなことがわかるのも、文学研究の面白さです。
私自身、英語そのものに興味を持ったのは、自分にとって訳のわからないものだったからです。わからない音があってわからない文字がある。その先に何があるんだろう。素朴な疑問から手を出したのだと思います。
おそらく学問に分け入るとは、自分にとって訳のわからないことにぶつかり、そのわからないを解明したくなる、ということだと思います。東工大生には、ぜひ自分にとっての訳のわからないものを見つけて、そして追いかけてほしいですね。
あちこちに手を出してみて、
その先にあるものを見つける

リベラルアーツを学ぶという上で必要なのは、義務感を持たずやる、ということだと思います。その意味では実学と対照的なのかもしれません。こういう職業につきたいから、こういう勉強をする。それが実学です。一方、あちこちに手を出しているうちに、たまたま出会ったひとつの学問に興味を覚える。その道筋を自由に辿りたくなる。リベラルアーツとは、そんな存在だと思います。
学校や教師に押し付けられた授業が、それぞれの人のリベラルアーツになっていくこともあります。たとえば、古典や漢文がそうですね。普段は英語以上に使いません。その意味では一見、実社会では役に立たなさそうに感じてしまう。
けれども、今使っている言葉の中には、和漢を通じた古典の伝統が深く厚く受け継がれています。詩文であれ、思想、歴史であれ、古典に触れるとそれを知ることができます。私自身、高校時代に古典を読むことのそういった面白さに気づきました。安直に切り分けた結果を見せるのではない、訳のわからないものの向こうに何かがあるだろうと思い、『老子』と『荘子』は高校の時にそこそこの時間をかけて読みました。
学生の中には、ばくぜんと英語力を高めたい、と相談にくる人もいます。そのとき、私の口からはとにかく、「英語については時間を使ってください」と言うことにしています。そのうえで、相談に来る学生には「自分の好きな本の英語の原書を1冊、完璧に読み上げてみたらどうだろう」、「これを読んでいたら生涯尊敬されるぞ」と話して、18世紀イギリスの歴史家ギボンの『ローマ帝国衰亡史』を薦めたりします。3,000ページある代物ですから、読み切ることはやはり難しい。ところが、読み切れなかったという苦い経験にしてもそれを共有する人たちに出会い、友として語り合う日がきっとあるはずなのです。
冗談めいた話はともかく、自分が関係している分野の最初の論文、その分野を生み出した論文を読んでみるのもいいと思います。まずは、自分はここまでやったんだと自慢できるものに挑戦してみることです。その点、学士課程の3年目で全員で受ける教養卒論は結構近い線をいくものかもしれません。教養卒論はそれこそ、自分でテーマを選んで、訳のわからないものを発見して、その先へ行こうという試みだと思いますから。
博士文系教養科目がもたらす横のつながりは、
10年後、20年後に生きてくる

東工大にはもう30年近くいますから、リベラルアーツ研究教育院所属の中でも、ベテランの一人になってしまいました。2016年にリベラルアーツ研究教育院ができて思うのは、一体感とまでは言いませんが、教室の中で学生同士が親しくなる空気が伝わってくるようになりました。特に私が担当する英語クラスは、学士課程1年目の学生が最初に出席する「東工大立志プロジェクト」のクラスと同じメンバーです。そのためこのクラスでは、思わぬケミストリーが誕生する可能性があるんですね。
博士後期課程の学生が参加する文系教養科目は、最初に説明された理念にとても共感しました。東工大のさまざまな専門分野のすでに研究者でもある学生を集めて、そこでお互いのリエゾンを作っていくという理念です。ずいぶん古い時代のことですが、自分の頃、それにあたるものは学際的な英語のサークル活動でした。他大学の専門分野の違う学生とも知り合って、その後30年付き合っています。すると、相手はあるいは学界の中心となり、あるいは大学の要職について仕組みを作り動かす側にまわっているわけです。
今、この科目に参加して、るつぼの中にいるようにメンバーとつながりを作っておけば、10年、20年後、世界各国の研究機関や大学、企業、行政などの現場にいる人たちと直に連絡がとれるような結びつきが生じます。学生時代の今は、あまり意識はしないと思いますが、将来、必ずその貴重さを実感する人がいると思います。学生には、その時のことを楽しみにしていてください、と言いたいですね。
今後の目標としては、まず、学生の自発的にこれをしたいという気持ちであったり、サインであったりを読み取って、それを授業の時間の中で引き出してあげるようにはしたいと思っています。今のところ、これだけは見せてあげたいという分量のほうに負けてしまって、そこまでは出来ていないのですが、なんとかやっていけたらと考えています。
![]()
原田 大介 准教授
研究分野 イギリス小説
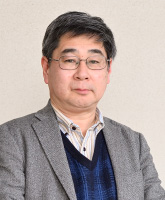
1986年東京大学英文科大学院修士課程修了。1988年より大阪市立大学で教壇に立ち、1991年、東京工業大学へ。講師、助教授を経て、2007年より現職。共訳書に『愛の博物誌』(ダイアン・アッカーマン著、河出書房新社、1998年)、『官能教育』全2冊(ピーター・ゲイ著、みすず書房、1999年)、『物語と歴史』(ヘイドン・ホワイト著、平凡社、2002年)などがある。







