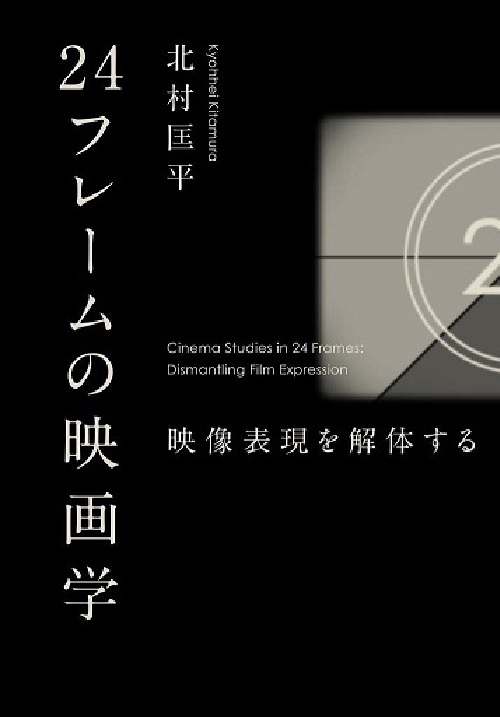リベラルアーツ研究教育院 News
映画/アニメからスター/アイドルまで 文化表象を横断して探求
【映像文化論、文化社会学、メディア論】北村 匡平 准教授

ハイカルチャーにサブカルチャー
文化を横断し、幅広く議論
僕は「表象文化論」を教えています。
脱領域的に美術、映画、哲学、文学、マンガ、アニメーションとさまざまな表現の領域を横断して文化現象を捉える学問です。これまでアカデミックな場であまり議論されてこなかった「サブカル」も関係なく分析対象になります。
学部1年生に向けた「表象文化論A」の授業では、絵画、写真、映画、映画スター、アイドル、アニメ―ションまで、近代以降の文化表象であれば、何でもトピックとして取り上げていきます。視聴覚的に表現される「表象」を幅広く扱うので、ディズニーランドやデパートをテーマにすることもあります。さまざまな映像やイメージを見て、学生たちと議論を行いながら文化を考察していきます。
それより専門的な「表象文化論B」と「表象文化論C」では、それぞれ異なるアプローチを取っています。前者は、映像文化論やメディア論の立場から、映画やテレビで活躍する有名人を社会学的に分析する講義。特にジェンダー・セクシュアリティ表象に着目していきます。戦前から活躍した、田中絹代、李香蘭、原節子といった映画スターからはじまり、山口百恵や松田聖子など70〜80年代のアイドル、90年代に活躍したアーティストの椎名林檎や宇多田ヒカル、2000年代以降のAKB48グループやももいろクローバーZなど著名な女性の有名人、女性グループを対象にしています。
映画やテレビなどのメディアのイメージだけではなく、同時代に他のメディアで構築される言説——ファン雑誌やアイドル雑誌、現代ならSNSなど——との関係も考えながら、彼女たちの名声がどのように価値づけされているかを分析することで、ジェンダー・セクシュアリティ規範やパフォーマンスの変遷を理解していきます。
たとえば、戦前・戦中の日本映画でスター女優の「男性や国家に献身する従順さ」が賞賛されていることを、実際に映像を観て、批評言説を確認していく。学生からは「映画は大昔の話で、いまは女性がとても強く、男女平等になっているので、リアリティがない」というコメントが来ます。そこで現在の男女平等をはかる「ジェンダー・ギャップ指数」でどれだけ日本の順位が国際的に低いか、日本の中高・大学などの教員や政治家の女性比率が世界のなかでどれほど低いかを確認していく。そうするとそれほど「大昔の話」でもないことが見えてくる。現代日本において、社会や国家が女性に求めているものは戦前とどれだけ違っているだろうか、という疑問も浮かんでくるわけです。
時代ごとに映画やテレビドラマの女性表象を社会学的なアプローチで考察することで、学生たちに社会に対する洞察を深めてもらう。それが授業の狙いの一つです。男子学生が9割近くを占める東工大において、学生たちに現代日本はいまだに男性優位社会なのだと認識してもらうことは、とても重要なことだと思っています。
アニメーションの新スタイル
“技術”が映画を変える

「表象文化論C」では、映像表現そのものを見ていく芸術学的なアプローチをとります。いわゆるフィルム・スタディーズのテクスト分析で、作家がどのような表現をし、その映像がいかなる美的効果をもつかを議論していきます。映画は誕生した当初、物語を伝える芸術だったわけではなく、動く映像を投影する技術(テクノロジー)それ自体が披露されたわけで、その発明は理工系の東工大生にとってきわめて親和性が高いはずです。映画は、工学的な技術によって支えられている表現なので、技術志向の強い学生たちにとっては、文系の学問でも意外としっくりくるのではないでしょうか。
授業では、映画やアニメーションにおける映像と音響、俳優の身体、カメラワーク、編集、照明など、映画の技術や表現について細かく分析していきます。どのような演出技法/撮影技法で優れた映像表現が生み出されているのか、それを考察するために映像を解体して、詳細に分析し、「だからこういう効果が得られるのだ」という授業内容には、強い関心を示す学生が多いですね。
アニメーション映画についても時間を割いて取り上げます。学生たちは宮崎駿や細田守、新海誠、あるいは日常的に京都アニメーションやシャフトの作るテレビアニメを見て育ってきた世代です。実写映画よりもアニメーションが好きだという人が多い。実際、映画館の興行収入を見ても、アニメーションが実写映画よりも年々ランキングの上位を占めるようになってきています。まさに現代の映像文化を考えるために必要不可欠な表現形態でしょう。レフ・マノヴィッチというニューメディア研究者が、デジタル映画はアニメーションの特殊なケースだと述べたように、現在、アニメーションと映画は非常に接近している。
たとえば、現代もっとも人気が高いアニメーション作家である新海誠の作品の特徴は、カメラの手ブレや、強い光が画面に入ってしまうフレアやゴーストなど、カメラで現実を捉えるときのような映像設計を積極的に取り入れて、独特の美しさとリアリティをアニメーションで表現しています。CGI/VFXなどの技術も現代の映画で欠かすことのできない表現ですし、IMAXなどの浸透によって映画館の視聴環境も大きく変化し、科学技術の発展が映画を新しいステージへと押し上げている。映像表現や技術は、文系/理系といった従来のディシプリンを越えて考察される必要があります。
ミュージシャン、役者、そしてメディア研究者へ
いま、僕は映画研究や批評をやっていますが、研究者の道を歩む前は、映画制作を学ぶ専門学校に通ったり、ストリートミュージシャンやバンド活動をしたりしていました。20代半ばまでは役者もしていて映画やCMなどにも出演した経験があるので、授業でそのときの話をすると驚かれます。僕の場合、研究者としてよりもまずミュージシャンや役者というエンタテインメントの現場で実際に作品を作る側にいたわけです。そのうえで改めて大学に入って理論を学び、研究者の道を歩むようになりました。映像の研究者でこうした経歴を持つ人間はかなり希なのではないでしょうか。だからこそ、自分にしかできないスタイルを確立して映画研究や批評活動をしていきたいと思っています。
日本の映画批評では、1980年頃から蓮實重彦による表層批評という革新的な批評のスタイルが登場し、多くの映画批評家に絶大な影響を及ぼしました。そんな蓮實的パラダイムの影響下にあって、どのような新しい批評が可能なのかを考えることが僕を含め、次世代の研究者・批評家に求められている役割だと考えています。なので、映像を分析する独自の方法論をじっくりと確立していきたいです。
現在、研究で取り組んでいる大きなテーマは、極論をいえば、日本人にとって「戦後」とは何だったのか、という問題です。映像テクストの分析だけではなく、その映像が立ち上がっていくコンテクストも含めて、大衆の欲望を体現するスターという表象から、日本の文化的価値の変遷を考察していきたい。言い換えれば、イメージの変化を見るだけではなく、言説分析を用いて、同時代的に語られた言葉の変遷をつぶさに見ながら大衆の意識を考察していくことです。
たとえば、京マチ子というスター女優について研究しています。「映画女優」という表象だけで見ると、京マチ子は戦後日本に圧倒的肉体美を見せつける強く主体的な女性イメージをもたらしました。ところが当時の雑誌の記事などを見ると、一転して淑やかで封建的なパーソナリティを作り上げている。映画の京マチ子と雑誌の京マチ子はまったく違うキャラクターなんですね。このスター女優を敗戦後の大衆文化から眺めると、映画のキャラクターと相反するパーソナリティが認知されていたからこそ、彼女はスターダムに上り詰めることができた。こうした複数のメディアを相互的に分析するアプローチによって、映画表象だけでは見えてこない戦後の日本人の意識や占領期の女性規範の実態が浮かび上がってきます。今後はアーティストやアイドル、YouTuberやバーチャルYouTuberなどについても考察を深めていきたいです。
20代の感受性の今こそ
「傷つくための旅」に出てほしい

リベラルアーツ研究教育院には2018年春から参加しました。多様な専門家が集まっているため、日々たくさんの刺激を受けています。ここに所属する教員の多様性をもっと社会に活かせないだろうか、と感じています。理数系が得意だけど文系科目も大好きという高校生もけっこういるはず。東工大では文系教養科目を多彩な先生たちに教わることができる、ということをぜひ多くの高校生に知ってほしい。通常、映画学の授業なんて高校では受けられないので、大学から出て高校で出張授業をもっとしてもいいと思います。勉強嫌いになる前に、大学で学問をすることがいかに楽しい営みかを伝えたいですね。
教育者としての目標は、東工大生たちが育ってきた環境、学んできた学校がどれほど小さな世界だったかを認識してもらい、外に飛び出させることです。僕の印象としては、東工大生はおとなしいけど実はきっちり批判的思考ができる人が多い。色んな大学で講義をしていると、こちらがびっくりするほど人の意見をスッと受け入れる若者もたくさんいるなかで、東工大生にコメントシートを書いてもらうと、ちゃんと反論を言ってくる。とても頼もしいなあ、と思います。
その一方で、首都圏の中高一貫校で英才教育を受けてきた人たちが多いのか、いささか画一的な思い込みをしている学生も結構見受けられます。1年生の必修科目「東工大立志プロジェクト」の授業でも、「女性は家庭を守るべき」「電車内で外国人がうるさいのは問題だ」などと、偏見を含むコメントをクラスで平気で発言する学生もいます。社会システムを維持したり経済成長を果たすためには、弱者を犠牲にしても仕方ない、といった反動的な意見を述べる学生も一定数います。
おとなしいけれど批判的思考を論理的に伝えることができる。一方でややもすると狭い偏見にとらわれていたり、良くも悪くもエリート意識が芽生えていたりする。そんな東工大生のキャラを理解しながら、授業での少人数のグループワークで、学生から気になる意見が出てきたら、それをクラス全体のテーマにして、より議論を深めてもらうようにしています。自分の考えが、もしかすると古い日本の規範を反復していて、世界的なポリティカル・コレクトネスの流れからズレてしまっているような現実を、仲間との議論によって気づいてもらう。
現代はインターネットを通じて、誰とでも簡単に繋がれて、関係が可視化でき、情報も知識もいつでも手に入れることができます。逆にいえば、だからこそとても閉塞的な時代といえます。情報だけが世界中に氾濫していて、いつでもアクセスできる。でも自分の体は一歩も外へ踏み出していない。パソコンやスマートフォンを通して「現実」を知った気でいる人が多い。だからこそ僕は、学生たちに旅に出てほしい、と思っています。
僕は18歳から上京してバックパッカーのように多くの国々を旅してきました。ところが、30代のいま海外に行くと、10代から20代前半にもっていた感受性がすでに失われていることに愕然とします。初めて訪れた場所でも、さまざまな経験をしているから、ある程度順応できたり、トラブルも回避できたりする。端的にいって慣れてしまう。でも、それでは面白くない。旅の本質的な目的は、いろんな人びとや文化に接し、多様な価値観に「触れること」、初めての環境に飛び込んで「傷つくこと」でもあるからです。
これまでの自分の物差しでは測れない「他者」と出会い、心を揺さぶられる経験こそが若い時期に大事だと思います。本を読んだり、ネットサーフィンするだけでは味わえない、リアルな体験が旅をすることで得られます。学生たちには、若いからこそ狭い世界から飛び出て、視野を広げ、失敗したり、傷ついたりしてほしい。そして自らの志を立てて学んでほしい。そう思っています。
![]()
北村 匡平 准教授
研究分野 映像文化論、文化社会学、メディア論

1982年、山口県生まれ。東京大学大学院学際情報学府修士課程修了、同大学博士課程単位取得満期退学。日本学術振興会特別研究員DC1を経て2018年から現職。主な著書に『スター女優の文化社会学――戦後日本が欲望した聖女と魔女』(作品社、第9回表象文化論学会奨励賞受賞)、『美と破壊の女優 京マチ子』(筑摩書房)、『24フレームの映画学――映像表現を解体する』(晃洋書房)、共編著に『川島雄三は二度生まれる』(水声社)、『リメイク映画の創造力』(水声社)、翻訳書に『黒澤明の羅生門――フィルムに籠めた告白と鎮魂』(ポール・アンドラ著・新潮社)など。
更新日 2021年6月7日